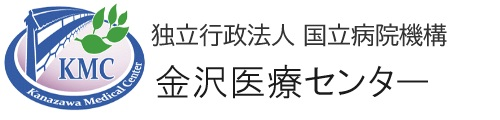サポート体制・指導医からのメッセージ
指導体制・サポート体制
支える力が違う。特色ある研修内容あなたがどうなりたいかに応じて、あらゆる方向から全力で支えます
①指導医体制
・研修医1名につき指導医1名が指導にあたりますが、科全体がチームでサポートします。
・メンター制を導入しています。安心して話せる場で、悩みや希望を整理することができます。
②ミニレクチャー
「その知識、今こそ身につけよう。」
月に数回、**各診療科のスペシャリストによる“ミニレクチャー”**を行っています。
テーマはさまざま。
たとえば──
• 救急で絶対に見逃せない疾患
• 創傷治療の基本とコツ
• 意外と誰も教えてくれない、でも臨床で大切な症候の見方・考え方 など
内容は、「研修医のときにこそ知っておきたかった」実践的な知識ばかり。
全科の経験豊富な指導医が、平日16時からの30分間で、ギュッと凝縮した知識と経験を届けてくれます。
時には「昔ヒヤッとした場面」を交えながらの解説も。
短い時間でも、明日からの臨床にすぐ役立つ学びが詰まっています。
令和7年度 ミニレクチャー一覧 2025.8時点
| 日付 | タイトル | 指導医師 |
| 4月21日 | ○縁○起&○会○釈 |
歯科口腔外科 |
| 5月7日 | 女性の腹痛 |
産婦人科 |
| 5月28日 | 緩和ケアと緩和ケア研修会について |
緩和ケア内科 |
| 6月4日 | 婦人科診察 |
産婦人科 |
| 6月11日 | 創傷のプライマリケア |
整形外科 |
| 6月13日 | こんな患者が歩いてくる 見逃せない 内分泌緊急症① |
内分泌・代謝内科 |
| 6月18日 | 単純CTでの出血の評価 |
放射線科 |
| 6月24日 | 便の話 |
消化器内科 |
| 6月25日 | こんな患者が歩いてくる 見逃せない 内分泌緊急症② |
内分泌・代謝内科 |
| 7月2日 | 妊婦健診 |
産婦人科 |
| 7月7日 | 病理検査のイロハ |
臨床検査科 |
| 7月9日 | 腸閉塞のCT |
放射線科 |
| 7月10日 | 歩いてQQに来る頚椎骨折 |
整形外科 |
| 7月31日 | 高齢者の脊椎圧迫骨折 |
麻酔科 |
| 8月1日 | 外用薬の使い方 |
皮膚科 |
| 8月6日 | グレードA帝王切開 |
産婦人科 |
③科を横断した基本技能トレーニング
例えば「感染演習 PPE 気管吸引 口腔吸引 ・採血・静脈ライン確保・シリンジ・輸液ポンプ・BLS・縫合・気管挿管・CV挿入 やAライン確保」など、研修中の科とは別に、系統的に学べる教育体制があります。
縫合練習は繰り返しおこないます。
また、医療従事者のための蘇生トレーニングコースであるICLS(Immediate Cardiac Life Support)を定期的に金沢医療センターで開催しており、金沢医療センターの研修医は無料で受講できます。受講することにより研修するにあたって必要不可欠な蘇生の基本的事項を習得できます。
さらに、日本内科学会主催の心肺蘇生講習会JMECC(Japanese Medical Emergency Care Course)も当院で開催しており、金沢医療センターの研修医は、無料で受講可能ができます。ICLSとは異なり、内科救急に特化した内容(心肺蘇生や重篤な急性疾患への対応)も学べるため、さらなるスキルアップが期待できます。
④勉強会の参加
また、立地柄、大学との交流が多く、大学主催の勉強会や講演会なども積極的に参加することができます。
⑤良質な医師を育てる研修シリーズ
全国の国立病院機構(医療センターなど)が主催となって、「良質な医師を育てる研修シリーズ」が定期的に全国各地で開催されます。金沢医療センターを含む国立病院機構に勤めている研修医のみが受講することができます。
様々な分野の研修を受けることにより知識を深め、同時に交流関係を広げることができます。交通費・宿泊費は全額免除されます。
(一例)
・病院勤務医に求められる総合内科診療スキル(国立病院機構研修センター)
・センスとスキルを身につけろ!未来を拓く消化器内科セミナー(呉医療センター)
・内科救急NHO-JMECC 指導者講習会(大阪南医療センター)
⑥積極的な学会参加
内科・外科など幅広い診療科で、座談会や北陸地方会、全国学会で研修医が発表する機会を頂けます。個人のやる気に応じて多くの学会発表を経験することによって研修医のうちから学会でのプレゼンテーション能力を高めることができます。
(一例)
第78回国立病院総合医学会 「術前診断に難渋した胆嚢捻転の2例」
第61回日本腹部救急医学会総会「特発性大網出血に緊急手術を行った1例」
第61回日本腹部救急医学会総会「右大腿ヘルニアの虫垂嵌頓に対して腹腔鏡下に二期的手術を行った一例」
第5回日本不整脈心電学会東海・北陸支部地方会「硫酸アトロピン投与により房室ブロックを回避し冷凍焼灼が可能となった房室結節リエントリー性頻脈の一例」
第65回日本呼吸器学会学術講演会「肝膿瘍とそれによる敗血症性肺塞栓症を来した侵襲性過粘稠性Klebsiella pneumoniae感染症の一例」
⑦2年次から1年次へ:伝える力も育てる
2年次研修医による1年次研修医へのレクチャーが始まりました。アウトプットすることで、今後指導する側になったときにも役立つ、さらなる力をつけています。臨床現場ですぐに役立つ知識をつけるためのレクチャーであり、指導医が伴走します。
研修担当医からのメッセージ
院長からみなさんへ
一人ひとりの“成長スタイル”に寄り添う研修
金沢医療センターには、全国各地から多様な経歴や背景を持つ研修医が集まっています。
「救急から専門分野まで幅広く経験し、一気に力を伸ばしたい」
「まずは基本をじっくり固め、着実に成長したい」
目指す姿は人それぞれ。私たちは、その思いに合わせて最適な環境と機会を用意します。
挑戦を望む人には限りないステージを。一歩ずつ進みたい人には着実なステップを。
あなたの個性やペースを大切にしながら、医師としての基盤をしっかり築けるよう、全力で支えます。ここで過ごす日々が、あなたの可能性を大きく広げる時間になりますように。
豊富な症例と恵まれた学びの場
当院は、日本三大名園の一つ「兼六園」に隣接し、金沢市中心部に位置する北陸地区の基幹病院です。がん・循環器(血管)を最重点分野に据え、24時間体制の小児救急にも対応。地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院として幅広い疾患と病態をカバーし、豊富な症例を経験できます。
救急搬送患者数は県内でも上位にあり、二次救急から心肺停止を含む三次救急まで対応。一般的な疾患から高度な専門疾患まで、臨床研修の到達目標を十分に満たせる環境です。外来診療・病棟管理・救急対応を通じ、診療技術や手技を確実に身につけることができます。
研修後も続くキャリア支援
当院は47学会・1機構の教育研修施設として認定を受け、卒後教育にも力を注いでいます。大学病院等と連携した後期研修連携プログラムにより、各人がめざす専門医取得に必要な経験を積むことができます。また、当院が基幹病院となる内科専門医コースを設定しており、将来のキャリア形成に向けて幅広い支援の体制が準備されています。
文化薫る金沢での2年間
当院は金沢21世紀美術館、国立工芸館、能楽堂など文化施設が集まる文教地区にあり、落ち着いた環境で研修に打ち込めます。
この地で過ごす2年間で、患者さんの病態を正確に把握し、診断・治療に自信を持ち、信頼される医師へと成長してください。私たちはあなたの挑戦と成長を心から歓迎します。
教育研修部長からみなさんへ
有意義で充実した研修を、あなたとともに
金沢医療センターは、精神科を含むほぼすべての診療科がそろった、北陸地区の中核を担う総合病院です。各科の垣根が低く、連携の良さとアットホームな雰囲気も、大きな魅力です。
研修では、臨床経験豊富な指導医のもとでの実践的な指導に加え、毎月の研修医集会や多彩なレクチャー、手技トレーニングなど、きめ細やかな教育体制を整えています。研修は一方的に与えられるものではなく、研修医と指導医がともに作り上げていくものです。研修内容は、研修医自身の声や希望を取り入れながら、常に進化し続けています。
研修医時代は、その後の医師としてのあり方に大きな影響を与える、かけがえのない時期です。
私たち指導医は、診療と並行しながらも、「2年後に一人前の医師として世に送り出す」ことを大きな使命と捉え、真摯に教育に関わり、また研修医の成長にも丁寧に寄り添っています。
研修医の成長を見届けることは、指導医にとって大きな喜びでもあります。教えることは、私たち自身の学びにもつながります。この好循環が、医療の質をさらに高める原動力になっていきます。
自主性を尊重しながら、指導医との対話の中で自分らしい研修を築いていける——それが、金沢医療センターの研修です。
自分らしく学び、確かな力をつける2年間。
この時間が、医師としてのあなたの未来を拓き、そして、何よりあなた自身が幸せになるための礎となることを心から願っています。
指導医からみなさんへ
指導医1
これまで若手医師、研修医、学生教育に携わらせてもらい、感じたことがあります。
当たり前のことですが、一人として同じ人間はおらず、みなさまざまな個性を持ち、背景も異なり、成長スピードもタイミングもそれぞれ違うということです。
また画一的なプログラムの研修ではついていけず、脱落する先生も一定数いることがわかりました。いろんな個性が混ざり合い、時にはぶつかり合い、思いもよらない良い結果をもたらすことも多く経験しました。
大変な努力をして医師にまでなったのに研修についていけず脱落する先生がいなくなってほしいと、強く思うようになりました。研修医の先生一人一人の思いを大切にし、個性を尊重し、その思いを活かすよう実際の研修に反映できたらとも考えるようになりました。
そして研修医の先生が中心となって、自分たちの目線で主体的、自主的にプログラムを修正していくことが理想的だなという思いに至りました。
ただ、これはとても難しいことだということも痛感しています。指導医も完璧ではなく、実際に研修医の先生と関わることで共に成長していきます。そして完璧な病院、研修環境はなく、自分たちで修正し、作っていくものだとも思います。研修プログラムである以上、最低限の基準、課題、ルールは絶対に必要ですが、ある程度の自由度をもって研修医の先生一人一人が主役として輝ける研修を共に考え、指導医と研修医でよりよい研修プログラム、環境を作っていければと考えています。
集まった素晴らしい個性の先生方が個性を活かして当院で新しいものを生み出し、よりよい研修環境を作っていってくれることを楽しみにしています。そのサポートができれば嬉しいです。
指導医2
当院は二次救急病院として、年間3,500~4,000台の救急車を受け入れている。対応しなくてはいけない疾患の幅は広く、発熱、腹痛、胸痛といったbasicなものはもちろん、精神疾患、皮膚疾患に対応できる能力も求められる。
このことからは内科を中心としたprimaryな対応をマスターしたい人にとって最もふさわしい環境と考えている。